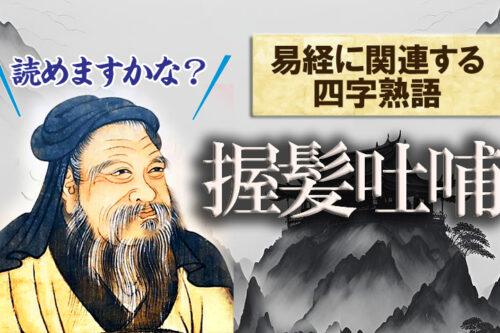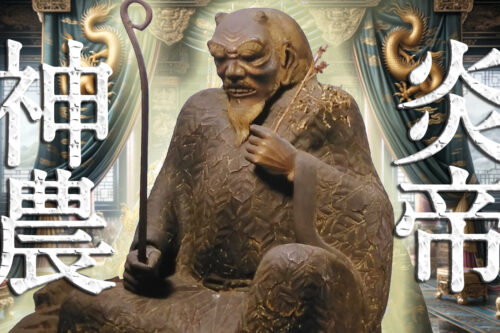「今日も暑いですね」。これが夏の挨拶になっています。私が、子供の頃の昭和も、たぶん暑かったのでしょうが、おやつの時間に、姉と弟で三人揃って、井戸で冷やしたスイカを縁側で楽しく食べたのを憶えています。
タネを飲み込むと、盲腸になるよなどと言われて、スイカの種を庭にプププと飛ばして遊んだり、顔にホクロだと言って、タネをつけて遊んだ思い出が、よみがえります。姉弟仲が良かったようでもあり、それなりに喧嘩もしました。スイカを冷やすために、家の北側勝手口辺りに井戸があり、キコキコと手動のポンプをくんだりしたものです。
美味しいものを親子兄弟で共に食して、楽しんでこそ、一家団欒があるものですね。
まずは自分。そして、次に家族を大切にすることが大事だと感じています。それは理解していますし、必要なことです。恥ずかしながら、愚凡軽率な私は、つい自分のことで手一杯になってしまうことが多いです。でも、それだけでは世の中が少し冷たく感じてしまいます。もっと、周りの人々にも目を向けて、温かい気持ちを広げていけたらいいな、と思っています。
自分さえ良ければいい、という主義から、他人のことをも考えるのが、☵☴水風井・井戸の美徳だと思います。心にゆとりがないと、他人のことまで考える余裕はありません。
町内のこと、自治体のこと、さらに言えば、社会のこと、国のこと。胸のどこかで、そこまでは、いいじゃないか、政治や、NPOがやるんじゃないか誰かがやってくれるだろう、政治や、NPOがやるんじゃないかと、おごった気持ちが出てきますが、そんな時は、水風井の教えを思い出します。何も立派でなくてもいいので、今の自分に出来ることから、社会に対する貢献、世の役に立つ、ということだと解釈しています。
井戸掘りに関する話として、日本各地には弘法大師・空海にまつわる伝説が残っていますね。空海は水に困っていた村人たちを救ったと言われています。唐に渡った際に、密教と同時に、井戸の見つけ方や掘り方を学び、それを日本に伝えたという話が有名です。
しかし、実際には唐よりずっと以前、古代中国の夏王朝の時代には、既に井戸を掘る技術があったとされています。四難卦では、すべて☵坎の水があり、天災として水に困ったことは想像できます。水風井の爻辞も末を遂げられないなど、あまり良くない意味の辞が多いような気がします。
さて、井戸の水は、澄んでいますが、底の泥を年に一度さらうと良いと聞いたことがあります。自分の心にある井戸も、濁り過ぎず、澄んだ水でありたいと思います。神道の大祓の儀や禊であったり、心の垢を落とす、クリーニングも大切ですね。また一方で、水清くして魚住まずというのも面白いですね。
さて、加藤大岳先生は、易経における卦の列順としては、☵☴水風井の次は☱☲澤火革を配していますが、序卦伝では、「井道は革めざるべからず」と警告しています。これはすなわち、古い井戸は汚濁するのが通例なので、その汚れを防ぐためには、絶えず清い水脈からの注入が必要だけれども、もしそれが出来なければ、そこから革命が誘発されることを指摘しているのでしょう。とおっしゃっています。
また、周時代の釣瓶は、木製ではなく土製・土器だったという説もあり、確かに、土器だったら、すぐには釣瓶の代わりはつくれません。それならば、☴巽の木製は何かというと、鄭氏の説は、桔槹(けっこう)という〔はねつるべ〕だとしていました。重力を利用して、水をくむわけです。その、はねつるべが壊れてしまうと凶であると。これを壊さないようにという戒めの言葉であったのです。井戸でも色々な種類があるものですね。
ある父親からの相談で、「娘が、彼氏を家に連れて来た。彼はどんな人かと、秘かに易を執ってください」。得卦が、水風井でした。この卦は、せっせと働いて、人のために尽力する井戸のような人物を象徴していて、彼の人柄を表しているように思えました。それをお話しると、ホッとしたことを悟られないように、笑顔を作り娘さんに話をされたそうです。とはいえ、「井戸」という言葉は若い世代にはあまり馴染みがないため、世代間のギャップを感じますね。(磯部周弦)
日本易学振興協会では、宇澤周峰先生が東京などで易経とともに、本格的な筮竹を使った周易・易占教室を開催しています。主に、三変筮法、六変筮法を中心にした易占法です。詳細はこちらからどうぞ。
日本易学振興協会への入会、お問合せは、こちらから