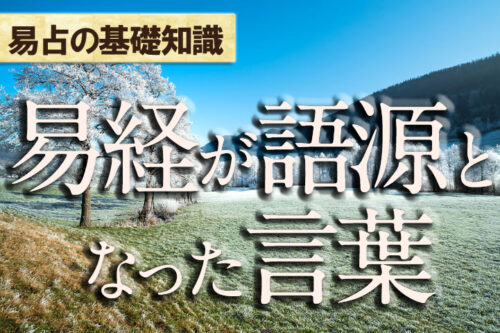易占の用具や用語について説明いたします。易占に当たって正式な筮法に用いる筮具は、筮竹(ぜいちく)・筮筒(ぜいとう)・ケロク器の三点をもって一式とします。その他に算木(さんぎ)があります。
筮竹とは、易占いに使う、竹を細くけずった棒状のものです。よく見ると先が太く手先が細くなっています。易経・易占を学んでくるとこの形状にも何か意味があることが分かると思います。易占ではこの易占で揲筮を行うには、筮竹を50本使います。揲筮とは、筮竹をさばいて数えることを言います。
筮竹の長さや色はいくつか種類があります。揲筮の為の易占用には、長さ九寸から一尺五寸位までが主流でしょうか。もっと長い筮竹もありますが、扱いづらくなります。
筮筒とは、筮竹を立てておく筒状の道具です。筮筒は竹や木で作ってあるものが多く、高さは四寸、径一寸五分位です。
50本の筮竹の中から、一本だけ抜きとり筮筒に立てます。この一本のことを「太極」と言います。
これは、易神の宿るところですので、丁寧に扱います。詳しくは筮操作の動画をご覧ください。
筮竹を使う易者さんの数が、減ってきました。
街角で見かける易者さんのなかには、簡易的な筮筒を使っていたり、筮竹は占い師としての演出小道具で実際には使わない人もいますが、やはり本格派の易者ならば筮竹をつかいたいものです。
ケロク器(掛扐器)は漢字では掛扐とも表記されるいわゆる筮竹台のことです。
筮操作を行う際に、筮竹を置くと次の動作に入りやすく、正統な易占では用いられます。筮竹を何本かまとめて置く便利な道具です。
三変筮法(略筮法)や六変筮法(中筮法)の場合は二山のケロク器を、本筮法(十八変筮法)には三山を通常用います。
また、掛扐器(ケロク器)は、周易翼伝のひとつ、繋辞伝の筮法を解いたところに「一を掛けて以て三に象り、之を揲うるに四を以てし、以て四時に象る。奇を扐に帰して以て閏に象る。五歳にして再閏あり。故に再扐して後に掛く」とあることから、付けられた名称とされています。
ちなみに、筮竹は自然素材ですので、筮筒に立てたままやケロク器に寝かせたままでいると、曲がってしまい癖がついてしまいます。定期的にお手入れを忘れずになさってください。
筮竹を用いた易占の手順は動画でも説明していますので、さらに興味がある方は、こちらもどうぞ。

日本易学振興協会では、八卦サイコロやイーチンタロットではなく、筮竹ひとすじで教えています。最近は、筮竹を使って易占いを行う「易者」が減ってきたと聞きます。
最後になりましたが、算木は、得た卦をならべるもので、材質は象牙、黒檀などの高級な石や木材も使われます。易の陰陽を現わすための六個の角材です。サイズは六分角(約1.7㎝)、長さ三寸六分(約10.7㎝)のものが多いようです。陰陽を示すので、陰のしるしには、螺鈿象嵌があしらわれる算木もあり、易者のステータスです。メモ帳に得た卦を書いた方が、早い点や集中力が途切れないなどの利点があります。
日本易学振興協会へのお問合せは、こちらから
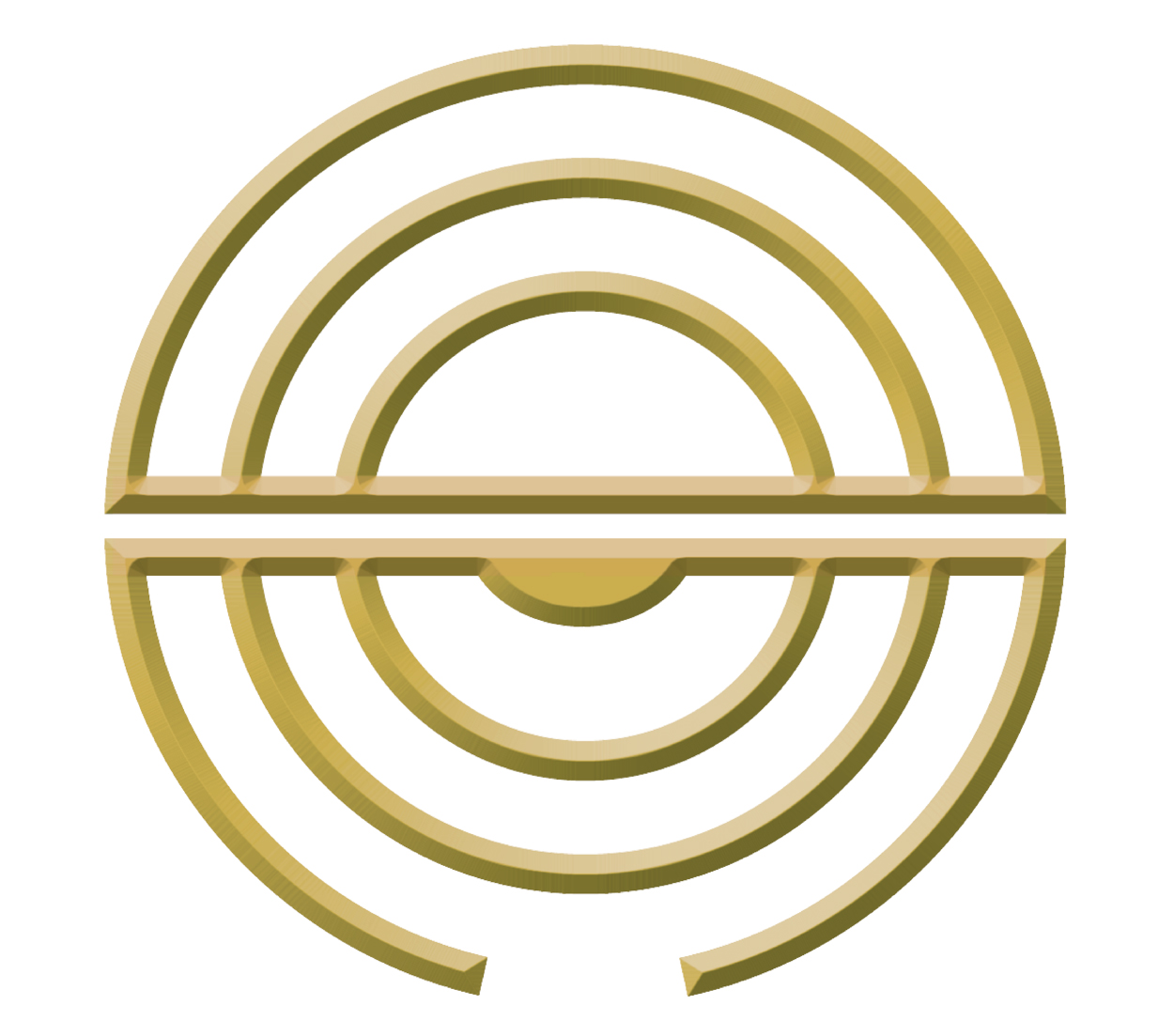
日本易学振興協会のサイトの管理運営担当です。まだまだ易占、易学の修行中、精進してまいります。伝統ある筮竹を使う周易を次の時代へつないでいきたいと思います。