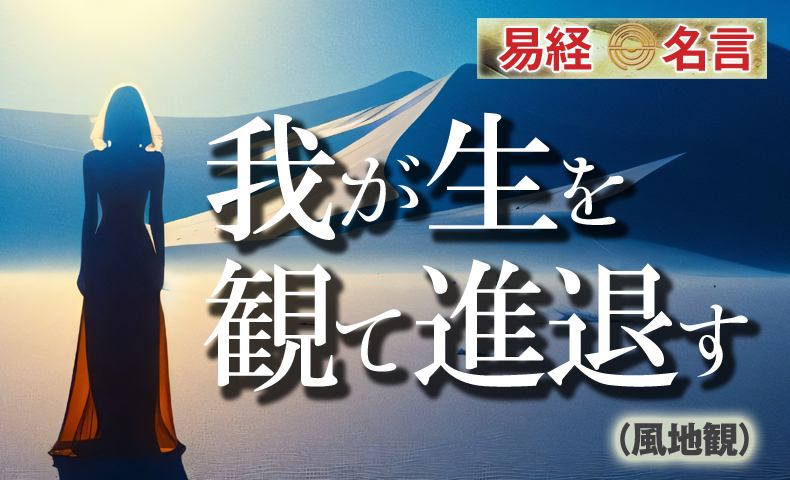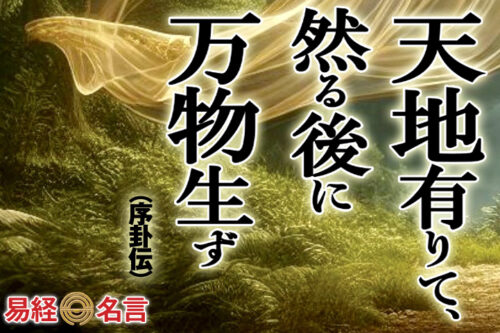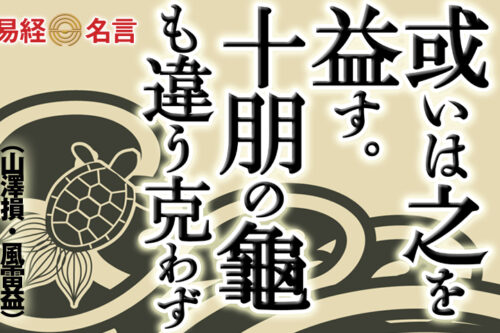易経は、名言の宝庫です。本卦から十翼の範囲で、特にこれは!という一節を選び出して、毎回掲載しております。易経を色々な角度から、かみしめるように味わって、より身近に、感じて頂ければ幸いです。
今回は〔我が生を観て進退す〕です。この辞は、☴☷風地観六三の爻辞からです。
訓読文は、そのままですが、次の通りです。
我が生を観て進退す
風地観の卦は、すべての爻辞に卦名の「観」が入っています。並べてみますと、旋律があって、とてもリズムがいいですね。
初爻 童観
二爻 闚い観る
三爻 我が生を観て進退す。
四爻 国の光を観る
五爻 我が生を観る
上爻 其の生を観る
わらべのような〔童観〕からはじまり、じっくり観る、自分を観る、国家を観る、国を観て、自分も観る、生き方を観直すというように、処世のための観察力というか、洞察力を説いています。
三爻〔我が生を観て進退す〕の解釈としては、それが、自分の生き方なのか?本当にそうなのか?ジッと見つめ直すように、何度も何度も自分の胸に聞いてみて、進退を決めるということです。特に、スマホやインターネットで情報過多になってしまった私たち現代人への、鋭い問いかけであると思います。
日々の仕事業務では、どうしても急ぎのことばかりに追われてしまい、重要なことを後回しにしまいがちです。しかし、時間をつくって、将来のことをイメージしたり、自分自身を内観することが、大切ですね。情報収集や、将来の自分への投資と思える勉強もその一環です。
週に1、2回でも、そのための時間を確保できれば理想的ですね。そのためには、仕組みづくりや、同意してくれるパートナーや家族の存在が大きな支えとなります.
また、自分を深く省みることで、自己の本質に迫ることができるはずです。内面の心の世界と、外面の現実が交差し、一つに繋がる時間が訪れるので、一瞬でも良いと思います。涼しい顔をして、こんなことを書いている私ですが、自分自身に言い聞かせています。
人間だけが、省みることができる
人間だけが、自分の内面の世界を省みることができる存在だと感じます。他の動物にはない、人間の智慧がそこにあり、その智慧から多くの気付きが得られるのです。
相談者の中でも、自分の素顔を知らないというか、つまり本当の自分を知らないという人が案外多いのです。
ただし、自分ばかりを責めても前に進むことは出来ませんし、自己正当化ばかりしていては、進歩がありません。
成り行きまかせの瞑想ではなく、易経を通じて自らを省みることによって、多くの教えを得ることができます。
他のどの国よりも、易経が広く受け入れられている日本は、世界一の易思想や哲理に合っている国だと言っても過言ではありません。誇らしげに言いましたが、これは、まさに日本人は自分自身との深い対話が、出来ているからではないでしょうか。
ところで、ハードボイルドな作風で知られる作家の北方謙三さんは、「ダイヤモンドの原石ではなく、道端にころがっているただの石ころだとしても、磨けば、それなりに光る」。と言いました。多くの人々に影響を与えた言葉です。この言葉も、決して自分を卑下して石ころにしている訳ではなく、彼の人生観や人間観を反映したものでしょう。努力や鍛錬を重ねることでどんな人でも成長し、才能を開花させ、輝くことができるというメッセージが込められています。
同じように、古くから日本の格言として使われていて「玉、磨かざれば光なし」などのことわざがあり、一般的な人生訓として広く使われている言葉です。磨けば、まさに、隠れていた才能であり、人間性が表れる瞬間です。
さて、私たちには〔自我〕と〔自己〕という二つの側面があり、普段は氷山の一角に過ぎない〔自我〕と向き合うことが多いですが、実はその無意識下にある〔自己〕と向き合うことこそが、真に重要です。
君子占わず、より、君子占う
何らかの決着や結論をつけなければならないとき、あるいはどうにも先に進めないと悩んだときこそ、この〔自己〕と向き合う必要があります。そうした時に、易に問えば、巫女である筮者の求めに応じてくれ、卦を示してくれます。それを可能な限り、読み取っていきます。易はヒントを与えて、私たちを導いてくれる存在です。
荀子や荘子の言葉「君子占わず」などを引き合いに出して、かたくなに占筮をやらず、易占より易学を上に見る学者さんもいらっしゃるそうですが、それは、易経を読み込んでいれば、小さな問題を多く占わずとも済むという意味だと解釈しています。本当に迷った時は、易占が力になります。
そして、易を研究し、奉じる立場の私たち易人が、易を立てる前に、座禅を組むのは、人生の真理に打ち込むには、好ましい風習だと思います。
『卦を執る時は、占的をハッキリさせなければなりません。ぼんやりした占的では、卦も判断も曖昧になってしまいます。迷う気持ちも解りますが、その状態で卦を立ててしまうと、かえって解らなくなってしまいます』と、先輩から教わった言葉です。今も、この言葉を胸に刻んでいます。
易の精神、すなわち易道というものを理解し、その易の道をも踏まえて人生を進んでいくのが、処世というものです。人生は矛盾に満ちていますが、それもまた自分が積み重ねてきた結果の表れでもあります。
朝起きてから仕事に出かけ、帰宅し、お風呂に入って寝るまで、私たちは常に〔動の世界〕に身を置いています。
そんな一日の中で、どこかで〔静の世界〕をつくることが重要です。平常の自分から脱け出すためには、お茶や華道、時間を見つけて、公園や庭園に行くのも良い方法です。
人生は決断の連続ですが、悲しいときに大事なことを決断してはいけませんし、勢いで、決断しても、正しい判断はできません。断ずるときこそ、静かな気持ちで臨みたいと思います。
〔我が生を観て進退す〕これこそが、易占法修練の要であり、たゆまぬ修業として求められるものなのでしょう。
せっかく易占術を身に付けたのですから、自分自身のことでも、他人のことでも科学や常識、努力の壁を越えるために、どうしたらよいか。それを易占によって答えを探りたいと思います。すると、越えるための手がかりが見えてくるのだと信じています。易経に生き、易経に教えられる毎日です。
日本易学振興協会では、東京などで本格的な筮竹を使った周易・易占教室を開催しています。詳細はこちらからどうぞ。
日本易学振興協会への入会、お問合せは、こちらから