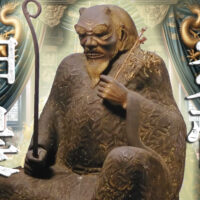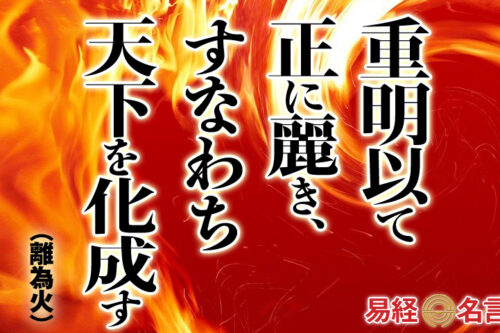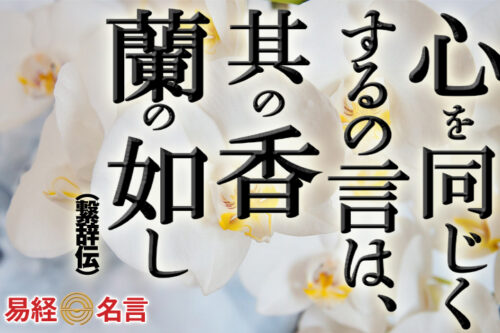易経は、名言の宝庫です。本卦から十翼の広い範囲で、特にこれは!という一節を選び出して、毎回掲載しております。易経を色々な角度から、かみしめるように味わって、より身近に、感じて頂ければ幸いです。
〔鳴鶴陰に在り、其の子之に和す〕
この言葉は、同学同好の諸兄姉方には、すでにお分かりの通り、☴☱風澤中孚九二の爻辞です。
毎朝、私はそっとベランダに出て、雀に餌をあげるのが、コロナでステイホームの時の日課でした。最初は警戒されないように、こっそりと置いていたのですが、最近では、私がまだベランダにいるうちに、チュンはパッと飛んできて、ためらうことなく、餌をついばみ始めるようになりました。
時々、チュンは数羽のヒナと一緒に連れてやってきます。ヒナといっても、もう飛べるようになり、見た目も親雀とほとんど変わらないくらいに大きくなっています。それでも、餌を前に、羽をパタパタと震わせ、「頂戴、頂戴」と口を大きく開けて親雀に甘えます。そんな姿を見るたびに、親雀がせっせと餌を与える様子が微笑ましく、心が和むのです。
まるで〔雀のお宿〕のような風景です。
そんな、ほっこりとした時間を過ごしながら、ふと、この☴☱風澤中孚二爻が、思い浮かびました。
訓み下し文は、次の通りです。
鳴鶴陰に在り。其の子之に和す。我に好爵有り。吾爾と之を靡にせん
素敵な表現ですよね。改めて申すまでもありませんが、この爻辞は、親鶴がピピピッと鳴くと草むらに隠れていた子鶴もそれに応えてピピピッと鳴く。心は鏡、こちらが笑うと相手も笑う。そんな親子のような、信頼関係を築いていきたいという場面です。
この風澤中孚の爻辞を通じて、人との関係も同じように信頼を築き、共鳴し合うことの大切さを感じさせられます。
また、鶴や雀と違って、カラスは気が荒く嫌われ者ですが、営巣やヒナを育てている時は、子供を大事に育てるため、〔慈鳥〕とも書くそうです。カラスは、童謡にもあるように、子煩悩な一面もあるようです。
いずれにしても、この爻辞を通じて、人との関係も同じように信頼を築き、共鳴し合うことの大切さを感じさせられます。
加藤大岳先生が、ある生徒さんの新築祝として、直筆の書を贈られたことがあったそうです。そこには、「孚攣如」と書かれ、落款が添えられていたとのことです。
☴☱風澤中孚五爻の爻辞「孚有りて攣如たり」から取られた語句です。易学に対しても、自分自身に対しても、無心の〔孚〕をもって向き合っていって欲しいと、加藤大岳先生は教えてくれているのでしょう。いかにも加藤大岳先生らしいですね。
生徒さんは、この言葉をただの飾りとしてではなく、これからの人生の指針として深く心に刻み込んだそうです。
「孚」は、易経の真骨頂
☴☱風澤中孚二爻は、親鶴が鳴いて子を呼び、子鶴がこれに応じて、鳴き交わしているという、うるわしい様子です。
その続きとして、好爵とは、好ましきものであり、自分の好爵を独り占めしないで、あなたと分かち与えたいという心情を表しています。このようにこの爻辞は、人とよろこびを分かち合うという意味があります。
さて、「まこと」は、日本の大和言葉でもあり、〔ま〕は、まんなか、まっすぐの意味で、真の意味です。そして、まさご、まこもの様に美称の意味もあります。大体、易経のなかでの孚と同一のものと言えます。
約6年前、日本易学振興協会の易学研究会において、「孚について」の研究発表が小島三周常任理事よりありました。とても参考になる濃い内容ですので、一部抜粋させて頂きます。
まずは、易経の彖辞、爻辞のなかで、〔孚〕という文字が使われている箇所がなんと、40箇所もあります。卦にして64卦中26卦にも登場しています。作易者はよほど「まこと」に重要視したことがうかがえます。
孚については、私利私欲がない心が〔孚〕であり、風澤中孚はその孚を代表する卦です。
「まこと」の字には、いくつか種類があり、それぞれ、少し意味が異なっています。
孚とは、それ自体の思惟的行動です。自分自身から発せられる思考による行動。
允とは、認める。承知する。許すという意味。
信とは、偽りがない。
実とは、中身が備わっていること。
誠とは、言葉や行いに作り事がない。
真とは、嘘のない自然のまま。
詳しくは、『岳易開成』既刊号をご覧頂くとして、それにしても、人間というものは、放っておくと、どうしても堕落してしまう生き物なのだと、私はつくづく感じます。これは、私自身のことを指しています。
いざ、自分が何かの問題と真剣に向き合わなければならない時が来るのですが、その問題を曖昧にしてしまう自分が居ます。自分のズルさ、臆病さが出て、やるべきことを先延ばしにして、やらない理由を巧く、自己正当化して、おさめてしまうのです。そのツケが今になってやってきて、やっと気付くことの多いこと。
しかし、そんな時、私は「まことをもって」という言葉を思い出します。結果がどうであれ、大切なのは、目の前の問題に対して、私は本当に「まこと」をもって対応しているのだろうか。他人にも、自分自身にも、まことを持っているか。自問自答しながら、そうありたいと、願う自分がいます。
やはり、「孚」という言葉は、『易経』の真骨頂だと言って良いでしょう。
信頼や誠実さを意味し、より深い意味を持つ表現ですね。一般的な「愛」という言葉は少し違った趣があり、特に易経の世界では、「孚」の方が易らしい表現だと思います。易経を深く読み、変化の時代にあっても、変わらない価値観に、軸足を置きたいものです。
日本易学振興協会では、東京などで本格的な筮竹を使った周易・易占教室を開催しています。詳細はこちらからどうぞ。
日本易学振興協会への入会、お問合せは、こちらから