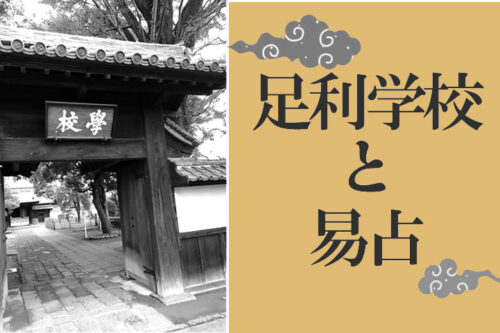郭沫若(かくまつじゃく)という人をご存知ですか?中国の作家であり、歴史家、考古学者です。加藤大岳先生の『易占法秘解』や『易学発秘』などの著書に、たびたび名前が上がるので、なんだか無性に興味がわき、千葉県市川市にある郭沫若記念館にお邪魔したことがあります。
郭沫若氏は、革命運動に身を投じていて、政府から危険視される存在となっていました。迫害を余儀なくされ、日本にいわば亡命、千葉に寓居していたそうです。日本での生活は、彼の思想や創作活動に大きな影響を与えました。古代の甲骨文や金文の研究発表を多く出しましたが、それらは、この亡命していた時期に、集中していました。
正直を言いますと、記念館では、あまり人間的な魅力は感じませんでしたが、「百花斉放・百家争鳴」などの詩は良かったです。本来の意味は、あらゆる考えの人が、自由に議論を活発に戦わせて良いものを造り上げるということですが、毛沢東は、この言葉を使って、文化大革命のスローガンとして、共産党の批判を歓迎すると言い放ったのですが、本当に批判が殺到したそうです。
それから後、ある日、神保町でぶらり散歩をしていたとき、中国専門書店の看板に目が留まりました。そこに書かれた文字は、郭沫若自身によるものだったからです。驚いて立ち尽くしました。日本にゆかりがあるのは分かっていましたが、それもそのはず、書店の人に尋ねてみると、この内山書店には、彼の歴史的ないきさつが隠されていることが分かりました。
内山書店の創業者である内山完造は、1927年、国民党に追われる郭沫若を上海でかくまったのです。郭氏は翌年、日本へ亡命。前述の、市川市に居を構え研究活動を行いながら、文学や考古学の発展に寄与しました。偶然にも、内山書店と郭沫若の浅からぬご縁も知ることができました。
小澤正元著『内山完造伝』から、少し紹介致します。
内山完造は、明治18年生まれ。幼い頃はやんちゃで、小学校を中退。そこから、様々な丁稚奉公を骨身を惜しまず、何でもやりました。母から『人は一生。名は末代までじゃで。必ず出世して故郷へ錦を着て来るんじゃぞ』と言われたことを心に刻み、人生を歩んでいったそうです。28歳のときに、現・参天製薬の販売員として、上海で暮らしていたところ、日本へ留学していた中国人の帰国が相次ぎ、本を欲しがる人々に向け、妻・美喜さんとともに、内山書店を開店しました。
そこで、郭沫若や、あの文豪の魯迅など文化人と深い親交を持つようになりました。
日中関係のもっとも険悪な時期に、上海を訪れる日本人の案内役をし、谷崎潤一郎や佐藤春夫も上海に来て、完造の世話で、日本の作家たちと中国文学者との交流の場を提供していたとの事です。
戦後、内山完造は74歳の生涯を閉じるまで、日中友好と国交回復実現のために心血を注ぎ、先頭に立って活躍。彼の情熱と日中文化交流の橋渡しとしての業績を称えるため、上海に墓碑が建立されています。
さて、郭沫若が日本に亡命していた、その最中、中国文学研究会の例会に於いて、約4時間にもわたって講演を行ったそうです。
一ツ橋にある学士会館には、加藤大岳先生も聴講され、そのときのことを『壮年気鋭の革命の闘士というよりも、やはり、学究の論客という風貌だった』と述懐されています。

郭沫若氏は、加藤大岳先生の質問にも応じ、「中国古代社会と易経の卦爻辞の中にうかがわれる、それとの対比」などについて論じ、彼の持つ豊かな知識を示しました。加藤大岳先生は、郭氏の講演を聞きながら、驚嘆したことがあったそうです。それは、詩経や書経を引用するのにメモ一つ持たず、長い章句を読み上げる〔記憶力〕に目を丸くされたとのことです。
人はそれぞれ運命があり、郭沫若が生きた、昭和初期と令和の今日とでは、ずいぶん違いますが、文化意識の点では、つなぐことが出来そうです。(磯部周弦)
日本易学振興協会では、宇澤周峰先生が東京などで易経とともに、本格的な筮竹を使った周易・易占教室を開催しています。主に、三変筮法、六変筮法を中心にした易占法です。詳細はこちらからどうぞ。
日本易学振興協会への入会、お問合せは、こちらから